この記事にあるリンクにはPRが含まれています。
やっとこさ、5巻目(トルコ・ギリシャ・地中海)を読み終えた。
けっこう楽しみにしていた巻だ。トルコ、ギリシャ、地中海なんて、きっと心浮き立つような美しい景色が続くのだろう。
p.21 アララット山、この山の名前を沢木さんに印象づけたのは、『エスピオナージ』という映画だった。
p.48 トルコでは街の人々とのちょっとしたやりとりが印象的だ。ここでは髭の老人が登場する。
p.54 写真を撮る機会がなかった理由
それは機会の有無というより、情熱の有無の問題だったかもしれない。確かに、カメラを構えることで土地の人々と言葉を交わすきっかけが摑める場合がある。しかし、それと同時に、風景によって喚起された思考の流れが中断されたり、人とのあいだに生まれかかった心理的なつながりに変化が起きてしまう危険性も少なくはないのだ。それでもなお写真を撮ろうとするのには、よほどの情熱とエネルギーを必要とする。
昨今は誰もが写真を撮りまくっている。私も例に漏れず。しかし、よく思うのは、カメラを観ていて、本物を見ることができているか、ということだ。一応みてはいるが、本当に見ているか?と思う。
写真を撮らない友人がぼそっと言ったことがあった。「あの人たちの心には何も残らない。」
その友人には、あらゆるものを写真におさめようと忙しく携帯を構えていた私に、「あなた病気だね」と言われたことがある。友人の事業を宣伝するために、ブログのネタを増やすべく撮っていたつもりであったが、それは言い訳だ。友人言う通り、病気なのだ。それは間違いない。
p.56 少年との出会い。少年に案内してもらい、黒海をみにいく沢木さん。
p.80 アンカラの女性、ゲンチャイに磯崎夫人からの伝言を伝えにいく沢木さん。
p.94 移動のバスで知り合ったキリスト髭の若者とフェリーに乗り、イスタンブールに着いた沢木さん。香港のときと同じように、成り行きから「オンボロ宿」に泊まり、香港を思い出している。
沢木さんは、香港で感じたような興奮がないのはなぜだろうと考えはじめる。
恐らく、最大の理由は時間にあった。毎日が祭りのようだったあの香港の日々から長い時間が経ち、私はいくつもの土地を経巡ることになった。その結果、何かを失うことになったのだ。
旅は人生に似ている。以前私がそんな言葉を眼にしたら、書いた人物を軽蔑しただろう。少なくとも、これまでの私だったら、旅を人生になぞらえるような物言いには滑稽さしか感じなかったはずだ。しかし、いま、私もまた、旅は人生に似ているという気がしはじめている。たぶん、本当に旅は人生に似ているのだ。どちらも何かを失うことなしに前に進むことはできない・・・・・・。
「どちらも何かを失うことなしに前に進むことはできない」。この部分にグッときた。
そうか。失ってきたのだ、私も。さまざまな旅をしてきた。自分の意志なのか、だれかの意志なのか忘れたが、毎月のように旅をしていた。旅するのを休んでいても、だれかが私を呼び、行かざるをえない状況ができて、行きたいと心から思わなくても、ときには行きたくないというなんとも暗い憂鬱さに後ろ髪をひかれながらも、何度も行かなくてはならなかった。
しかしどんな旅であれ、人と会い、食べ、ときに喧嘩し、泣き、笑い、交代で運転し、変な宿で眠り、好奇心にまかせて移動する旅は、五感のセンサーを磨くのにいくらか役に立ってくれたと思う。
私の移動は旅だけではない。二拠点、ときには三拠点で生活しながら、どこで寝泊まりしていても、そこに住所があっても、どこでも旅をしているような錯覚を起こす。朝ベッドで目覚めた瞬間に、今日はどこにいるんだっけ、と思うことも頻繁にある。寝起きのぼーっとした頭で、いったい私はいま、どこのベッドで目覚めようとしているのか?と。
住んでいる土地を歩いていても、これは旅の一部なのだと感じる。いまはここにいるが、ゆくゆくは移動していくだろう。一時的にこの町にいるに過ぎず、滞在してひととおり巡り終えたら、また次の土地で新たな日々が待っている。好んでこの生活をしているのか、自分でもわからないが、これをやめることができないということは、おそらく好きなのだ。新たな土地、新たな食、新たな出会い、新たな町。しかしそうやって土地から土地へと巡っているうちに、人との出会いも含めて多くのものを得ている一方、やはり私も、知らず知らずのうちに、失っているものがあるのだ。
p.100 気に入った食事が記されている。イスタンブールの食事は美味しそうで、偏食の私も楽しい旅ができそうな気がした。
p.111 プディング・ショップの記述がある
p.121-122 プディング・ショップを出て、ひさしぶりに、「前へ進もうか」という言葉を発し、「旅を続けよう」と思った沢木さん。
p.130 「危険に対する鈍感さ」「自分の命に対して次第に無関心になりつつある」
p.138 夕闇の中、橋を渡って国を越える沢木さん。
p.162 アクロポリスの丘で観光客と出会ったあと、「アテネのどこを歩いても、なんとなく気持が乗らなくなってしまった」。「観光地としてのアテネがアテネのすべてではないはずなのに、どこを歩いてもアクロポリスの丘と同じ乾いた死臭が漂っているような気がしてならないのだ」。「何かが足らない」。
p.166-167 「何かが起きそうで起こらない」。茶とチャイの話。
それにしても、沢木さんは旅でチャイをよく飲む。私ももともとチャイが好きだが、読んでいるうちに、以前よりも頻繁にチャイを所望するようになった。
p.178-179 映画『エレクトラ』、ミケーネの宮殿跡。
高校のころ、沢木さんはよく有楽町の映画館でヨーロッパの映画を観ていたという。ここで挙げられていた映画は、『長距離ランナーの孤独』、『去年マリエンバードで』、『蜜の味』。
大学生になり、アイスキュロスやギリシャ悲劇を読んで、やっとエレクトラの物語を理解したという。
私も『エレクトラ』という映画を観てみたいと思う。そして読んでみたいギリシャ悲劇。
p.180-186 この巻で個人的にもっとも印象的な部分だ。
スパルタで老人との出会い。
古代のスパルタがあった場所には、ほとんど何も残ってなかった。
しかしそこで、沢木さんはアテネのアクロポリスの丘に登ったときよりも「はるかに強いうねりのある感情が沸き起こ」るのを感じた。
滅びたものは滅びるに任せておけばいいのだ。滅びのあとに生まれるものがあれば生まれればいい。滅びたものを未練に残しておくことはないのだ。スパルタは死んでいた。しかし、このスパルタの徹底して潔い死には、アテネのアクロポリスのあの壮大な骸(むくろ)のような美しさには打ち勝てないのだ
目に見える象徴的な何かが残っているよりも、潔く何も残っていないほうが、心に強い何かを印象づけることがある。それは、旅の写真を撮らないということにも繋がるように思う。
その後、老人との会話が始まる。次のことばは老人のことばだ。
あの栄光の都市国家スパルタは何も残そうとしなかった。ここにあるこの石ころの他には。ギリシャの歴史家も言っている。スパルタが滅びた後のスパルタには、かつてあのスパルタが存在していたという痕跡すら残っていないかもしれない、と。実際それが私の気に入っている点でもあるのだよ・・・・・・。
老人に促されるまま、ミストラへ向かう沢木さん。
そこで、タイの古都アユタヤを思い出す。雨上がり、「腹の底から美しい」と思う光景。
同時に沢木さんは、「このような光景に遭遇するために旅をしているのではない」と思った。
「このような風景でないとしたら、いったい何だというのか」。
そしてふと、スパルタで出会った、さきほどの老人を思い出す。「彼はあそこで何をしていたのだろう」。
ただぼんやりしていただけに見えた老人は、実は話し相手になりそうな人を待っていたのではないか。テレビも新刊本も必要ないと話していたが、「しかし、彼もまた人だけは必要としていたのではなかったか」。
「そのとき私は、自分が胸のうちで、彼もまた、と呟いていたことに気がついた。そう、彼もまた、と・・・・・・」
沢木さんは、旅でよく人と出会う。それがこの『深夜特急』というシリーズを大変面白くさせているように思う。もちろん沢木さんの内面に流れる精神のようなもの、沢木さんの綴る人生哲学というか旅哲学のようなものが、多くの人々の心を惹きつけるのもあるが、私は自分で旅をしているときに、それほど多くの人と話をしないので、これほど多くの人に出会っている沢木さんが単純に羨ましいようにも思う。沢木さんだから出会えたんだと思わなくもないが、これからは、私ももっと旅の最中に人に話しかけてみよう。そしていつか、心温まるエピソードも生まれるかもしれないと、今は思う。心に残る旅を続けることを、あきらめてしまわずに。
p.196-197
オリンピアの競技場。
そこで、男と走って競争する沢木さん。十代のころ、沢木さんは短距離の選手だったという。
走っているうちに、二百メートルも全力疾走できず、草の上に倒れ込み、体力が落ちていることに気づく沢木さん。
ギリシャに入って何かが変わったと感じていた沢木さんだが、「その時、ふと、変わったのは土地ではなく、私なのかもしれないと思った」。
p.198
「あるいは、変わったのは、土地でもなく、私でもなく、旅そのものなのかもしれなかった。」
「旅がもし本当に人生に似ているものなら、旅には旅の生涯というものがあるのかもしれない。」
幼年期、少年期、青年期、壮年期、そして老年期。
沢木さんは、これまでの旅を思い返す。「何を経験しても新鮮で、どんな些細なことでも心を震わせていた時期はすでに終わっていたのだ。そのかわりに、辿ってきた土地の記憶だけが鮮明になってくる」。
「いずれにしても、やがてこの旅にも終わりがくる」。
このとき初めて、旅の終わりについて考えはじめる沢木さん。
p.199-201
とくに訪れたい土地を考えず、「いくつかの偶然によって」、さまざまな土地に立ち寄ってきた沢木さんだが、ここだけは訪れてみたい、と思っていた土地があった。
それが、「ギリシャの田舎、ペロポネソス半島」
なぜそこへ訪れたかったのか。沢木さんが少年時代に読んだ、一冊の旅行記について語られる。
沢木さんのお父様が初めて買ってくれた本だそうだ。
巻末の対談でふたたびこの本について触れられるが、サブタイトルは「世界一周一日一ドル旅行」だそうだ。
その旅行記の中で、沢木さんが気に入っていたのが、ギリシャの章だった。
その章には、日本人がその半島で現地の人と出会う話が綴られていた。
沢木さんもその半島へいけば、「あのような幸福な出会いがあるかもしれない」と思い、その眼で確かめてみたいと思っていた。
しかしその半島を「ほとんど一周したにもかかわらず、夢見たようなことは何ひとつ起こらなかった」。
これは、旅をしていると、私もよく感じることがあった。何か起こると思ってそこへいって、起こりそうで何も起こらない。だからといって、行かずに終わることはできず、行ってみて、なにも起こらなければ、起こらないということを体験するだけでも十分なのだ、と思う。
このあと、沢木さんには人との出会いがあり、結果的には旅の思い出になるような「幸福な出会い」となる。
p.213「この一夜が旅の神様が与えてくれた最後の贈り物なのかもしれないな」
p.218 ポール・ギャリコの小説、ポセイドン号、 というのが出てくる。その本、読んでみたい。
p.220 ギリシャからイタリアへ渡ろうと船に乗っている沢木さん。その船の上で感じていたのは、「安らかさではなく、不思議なことに深い喪失感だったのです」。「体が空っぽになってしまったような虚しさが僕をとらえていました」。
このあたりは、この巻で最後の章であり、「絹と酒」というタイトルのつけられた章で、手紙形式で綴られる。
p.225-226
シルクロードは「多くの危険に満ちた道」。その危険というのは、沢木さんが言いたい意味は、旅にともなう身の危険というのとは異なる。その危険の意味は、次のように語られる。
「長い道程(みちのり)の果てに、オアシスのように現れてくる砂漠の中の町で、ふと出会う僕と同じような旅を続けている若者たちは、例外なく体中に濃い疲労を滲ませていました。(中略)疲労は好奇心を磨耗させ、外界にたいして無関心にさせてしまいます。旅の目的すら失い、ただ町から町へ移動することだけが唯一の目的となってしまいます。(中略)「ポール・ニザンのいう「一歩踏みはずせば、いっさいが若者をだめにしてしまう」状態に陥っていたのです」。
西への途上で出会う誰もが危うさを秘めていました。とりわけそれがひとり旅である場合はその危うさが際立っていました。一年を越える旅を続けていればなおのことでした。しかし、と一方では思うのです。このような危うさをはらむことのない旅とはいったい何なのか、と。
ポール・ニザン、その本、気になります。あとで調べようと思い、メモ。
ポール・ニザン『アデン・アラビア』という本の中にあるようだ。下記のブログURL参照。
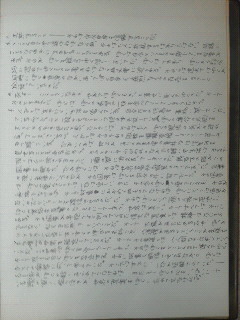
p.226-228
そして、現代のシルクロード旅行記について、シルクロードを賛美するものはあれど、沢木さんのいう意味での危険について、それらの旅行記の中で「語られることは決してない」と記されている。
たしかに、かつてのシルクロードがどのような用途で使われていたとか、歴史に思いを馳せてみると、はたしてシルクロード旅行記に綴られているような、旅の「道」であっただろうかと思う。
沢木さんは、「何かが違う」と思い始める。
沢木さんが出会った若者たちにとって、シルクロードは、単なる道にすぎなかったのだと。
滅びるものは滅びるにまかせておけばいい。現代にシルクロードを甦らせ、息づかせるのは、学者や作家などの成熟した大人ではなく、ただ道を道として歩く、歴史にも風土にも知識のない彼らなのかもしれません。彼らがその道の途中で見たいものがあるとすれば、仏塔でもモスクでもなく、恐らくそれは自分自身であるはずです。
それが見えないままに、道の往来の途中でついに崩れ落ちる者も出てきます。(中略)死んでいったカトマンズの若者と、そうした彼らとのあいだに差異などありはしないのです。死ななくて済んだとすれば、それはたまたま死と縁が薄かったというにすぎません。
ここでもまた、スパルタと同じく、「滅びるものは滅びるにまかせて・・・」というフレーズが出てくる。私はこのフレーズが好きだ。旅の途上で崩れ落ちても落ちなくても、人もまた、間違いなくいつか滅びる生き物である。何かが見えたとしてもそれは幻想あるいは幻覚かもしれない。
おそらく、どのような旅の路も、いまを生きているものたちが歩くただの道に過ぎない。そこで漂泊の旅を続ける私のような者たちが何か本当に本気で見たいものがあるとすれば、たしかにそれは、名所旧跡や観光スポットなどではないと頷く。
「取り返しのつかない刻(とき)が過ぎていってしまったのではないか」「もうこのような、自分の像を求めてほっつき歩くという、臆面もない行為をしつづけるといった日々が、二度と許されるとは思えまん」。
そして沢木さんは、喪失感の実態に思い至る。
それは「終わってしまった」ということでした。終わってしまったのです。(中略)自分の像を探しながら、自分の存在を滅ぼしつくすという、至福の刻の持てる機会を、僕はついに失ってしまったのです。
うーん、つくづく思う。こんな旅、してみたかった。いまからでは、さすがに遅いだろうか。
p.237-238
巻末の対談。
ここで、一日一ドルの旅について書かれた本のタイトルが、小田実の『何でも見てやろう』だとわかる。
一日一ドルで暮らすための具体的な方法が書かれていなかったことに失望した沢木さんだが、「『深夜特急』の読者もあれを読んでも何も外国のことはわからなかったということになるんじゃないか、という気がするんですよ」と語る。
それについて、対談相手の高田宏さんは、「人生論として読むんだな」と応じている。「人間はいかに生きるべきか、という昔からの問いをこの『深夜特急』に読むという読者は相当いると思うな」と。
まさに、そのように読んでいると思います、私。
p.239
沢木さん:「旅を即文章化する必要というのは全くないんですね。旅を反芻しながら、或いは鍛えながら文字化していくということは以前には多くなされていたんだ。」
そうか、すぐに書かなくてもいいんだ、と書くのが遅い私は思う。書いておきたい旅もあるが、すぐに書かなくてもいいんだ、と。
p.240-241
沢木さん:(現代の日本の紀行文において)「帰りが決まっていない旅の紀行文というのはほぼ皆無」
しかし、近世においては、『おくのほそ道』など、「文学的伝統」があり、「それを受け継いだ紀行文が途絶えてしまっている」。
高田さん:「『おくのほそ道』の最初の方で「古人も多く旅に死するあり」と言ってますよね。自分も旅の途中で死ぬ可能性を考えて、家も手ばなして出かけていますね。」
いやぁ、なかなか読み応えのある第5巻でした。ゆっくり読む時間を過ごさせてくれた某喫茶店に感謝します。
この巻のメモは以上です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/27fb6e25.4621383e.27fb6e27.6da6d997/?me_id=1213310&item_id=20085418&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5325%2F9784101235325.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2e6ef8d6.6b3fad2d.2e6ef8d7.5afd99bb/?me_id=1269077&item_id=10006933&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgreens-gc%2Fcabinet%2Fow%2Fow6411.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3cac7166.b4ce082b.3cac7167.67c77c87/?me_id=1220207&item_id=10021150&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faimere%2Fcabinet%2Ffood%2F05391270%2Fimgrc0113552709.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント